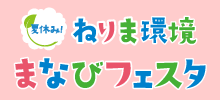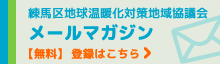令和7年度 環境月間講演会(講演記録 抜粋)
「図鑑から読み解く 豊かな地球と生き物たち」はじめに
講師:松原由幸 博士(株式会社Gakken図鑑チーム編集長)
【プロフィール】
愛知県出身。平成29年(2017年)、名古屋大学大学院生命理学専攻博士後期課程修了(理学博士)。同年学研プラス(現・株式会社Gakken)に入社。ドリルや参考書の編集を経て図鑑編集部に所属。「学研の図鑑LIVE」シリーズで恐竜などのテーマを担当し、現在は図鑑チーム編集長を務める。

講演中の松原氏
はじめに
皆さん、こんにちは。たくさんの方々にお集まりいただき、大変嬉しいです。私は、株式会社Gakken(がっけん)という出版社から来ました。松原と言います。今日は「図鑑から読み解く 豊かな地球と生き物たち」というテーマでお話させていただきます。
大きく2つのお話をしたいと思います。1つ目はどうやって図鑑を作っているの?というお話。2つ目は世界の生き物クイズ大会として、クイズを解いてもらいたいと思います。クイズ大会が終わった後は、質問を受け付けたいと思っています。図鑑のこと、生き物のこと、そして恐竜のことなど、質問いただけたら頑張って答えたいと思います。
自己紹介
私は、本を作る仕事をしています。ここにある『恐竜最強王図鑑』をご存知ですか? この本の絵は、だいたい私が描いています。以前、会社に入る前、絵を描く仕事をしていたんです。
現在は、『学研の図鑑LIVE(ライブ)』というシリーズの編集長をしていて、中でも『恐竜』『人体』は私が自分で編集したものです。また、図鑑を作る前は小学生向けのドリル、例えば、『ドラゴンドリル』シリーズなども作っていました。
全国各地でイベントも開催しています。昨年は夏休みに「LIVE恐竜全国ツアー」を実施しました。北は北海道から、先月行った熊本まで、全国を回って、皆さんと一緒に図鑑の話しをする活動をしています。
最近ではYouTubeで、恐竜や生き物の解説もしています。興味のある方はご覧ください。
https://www.youtube.com/@live2733/videos

私と図鑑
今日は、小さいお友達がたくさんご来場されているので、私の子どもの頃の話をさせてください。私も図鑑が大好きで、絵を描くことがとても好きな子どもでした。
ここにあるのは、水玉模様の表紙が特徴の昔の学研の図鑑です。皆さんのお父さんお母さんが子どもの頃、実はこの図鑑が販売されていました。この恐竜図鑑、30年前に発売されたものですが、私が3歳ぐらいの時に買ってもらって、それこそボロボロになるまで読み込みました。
この2枚の絵は、私の実家にあった絵を写真に撮ってきたものですが、恐竜図鑑の絵を描き写して描いたものです。骨の絵なども描くのが好きな子どもでした。
その後、さまざまな経験を経て生き物がとっても好きになり、大学、そして大学院へと進みました。これはおよそ10年前の写真ですが、動物の骨の研究で博士号を取得しました。その後、今の株式会社Gakkenに入社し、本を作っているという人間です。
『学研の図鑑LIVE』シリーズ編集長として
現在、私は『学研の図鑑LIVE』シリーズの編集長をしています。学研の図鑑は約50年の歴史がありますが、その中で『学研の図鑑LIVE』は一番新しい図鑑シリーズです。
会場の皆さんのなかで、学研の図鑑を読んだことがある、という人はいますか? 読んでくれている人がたくさんいますね。皆さんがご自宅や学校の図書館、本屋さんで見るような図鑑を作るのが、私の仕事です。
なぜ今日この場でお話をするのかというと、今日の講演会が「地球環境を考えよう」というテーマだからです。図鑑を読んで、さまざまなことを知るということが、地球を大切にする、環境を大切にすることの最初の一歩だと私は考えています。このことについては、今日の後半でお話したいと思います。
いろいろな図鑑
世の中にはいろんな図鑑があります。昆虫、恐竜、危険生物、魚など、さまざまなテーマがありますね。例えば、昆虫の図鑑には、たくさんの昆虫が載っています。昆虫は、皆さんが公園などに行くと、たぶん一番目に触れる「動く生き物」だと思います。最も身近で最もたくさんの種類がいる動物は、実は昆虫なのです。ですから昆虫図鑑を開くと、とても面白いですよ。
これは私が実際に作った恐竜の図鑑です。恐竜はもういませんよね。実は、鳥として生き残っていますが、大多数の恐竜は6600万年前に絶滅してしまいました。そんな今いない恐竜たちの姿をイラストなどで知ることができるのが、恐竜図鑑です。
星と星座、人体の図鑑
星と星座の図鑑は、夜空の写真が載っていて、星を結ぶと星座になることや、星座にまつわるギリシャ神話の話などが載っています。
続いて人体の図鑑。これは私たちの体の中、普段は見えない体の中について知ることができる図鑑です。これは「胃」のページです。お腹がすくと「ギュルギュルギュル」と鳴ることがありますよね。だいたいこのあたりに胃という内臓が入っていて、食べたご飯がここで消化されます。このように見えない世界を伝えるのが人体の図鑑です。
図鑑の制作過程
「学研の図鑑LIVE」シリーズの『恐竜新版』には、およそ420種類の恐竜が載っています。ちなみに、今、恐竜が何種類ぐらい見つかっているか知っていますか?
恐竜は今、1,000種類くらい見つかっています。1,000種類全部を図鑑に載せると分厚くなって、読むのが大変になってしまいます。そこで、およそ半分の約420種の恐竜などが載っている図鑑を作りました。
これはティラノサウルスですね。大人気の恐竜で、大きく載せています。他にもヴェロキラプトル。ヴェロキラプトルを聞いたことがある人はいますか?
映画「ジュラシック・ワールド」や「ジュラシック・パーク」で大活躍する恐竜です。こういう小型の肉食恐竜も載っています。その他にも、アパトサウルスやスーパーサウルスといった首が長い恐竜も載っています。
いろいろな恐竜たち
これは何? ステゴサウルスです。背中に大きな骨の板がならんでいます。しかも尻尾の先には、大きな骨のトゲトゲがあります。このトゲトゲを振り回して、大きなアロサウルスのような恐竜に襲われた時も、これで戦っていたといわれています。
では、これは何? アンキロサウルスという鎧竜の仲間です。これはきっと、皆さん知っていますよね? そう、トリケラトプスです!
トリケラトプスは、大きな頭に3本の角(つの)が特徴の角竜の仲間です。ティラノサウルスと同じ時代、同じ場所で暮らしていたといわれています。
このように、図鑑にはたくさんの恐竜が載っています。これは化石を載せているページです。いろいろなページがあります。これらはすべて、人の手で作られています。では、「図鑑はどうやって作るのか」という本題に入っていこうと思います。
図鑑制作にかかる時間
クイズです。図鑑を作るのにどれくらいの時間がかかっていると思いますか?
①2か月
②1年
③2年
正解は、3番目の「2年」でした。
恐竜図鑑は2年間かけて作りました。ですから、今、小学校1年生のお友達が小学校3年生になるぐらいの長い時間をかけて作っています。
まず最初に行うのは、「どの恐竜をのせるか決める」ことです。先ほど、恐竜は1,000種類いると言いましたが、その1,000種類からどうやって400種類に絞ろうか? どれを載せようか? と考えるところから始めます。これは恐竜だけでなく、昆虫図鑑を作る時も、動物図鑑を作る時も、まず「どの生き物を図鑑に載せたら良いか」を考えるところから始めます。
図鑑制作の手順
載せる生き物たちを決めたら、次にやることは「恐竜の説明文を書いてもらう」ことです。恐竜の近くに、「ティラノサウルスはこういう恐竜です」「ステゴサウルスはこういう恐竜です」といった説明文が書いてあります。
実はこれ、私が書いたわけではありません。もっともっと詳しい先生たちに書いてもらいます。その先生たちの仕事の名前は「研究者」で、大学や博物館などで働いています。その先生たちに、それぞれの恐竜の説明を書いてもらうようにお願いします。
「恐竜の絵をかいてもらう」という仕事もあります。恐竜はもういませんよね。ですから、写真を撮ることはできません。そのため、恐竜の姿形を絵で表してもらうイラストレーターさん、つまり、絵を描くのが得意な方にお願いして、図鑑に載せる絵を描いてもらいます。
また、恐竜図鑑には、化石の写真がたくさん載っていますよね。「化石の写真を撮りに行く」ということもします。その時は、写真を撮るのが得意なカメラマンさんと一緒に、博物館に行って写真を撮ってきます。これは上野にある国立科学博物館という大きな博物館に行って撮った写真です。ティラノサウルスの骨と、ステゴサウルスの背中の骨です。
図鑑を形にする人々
ここまでで、「説明の文章ができました」「イラストもできました」「写真も撮れました」。
これらを、皆さんが最終的に読めるようなページの状態にまとめるのが最後の作業です。これをしてくれるのが、デザイナーという仕事の人たちです(「文、絵、写真をならべる」)。
集めたいろいろな素材や材料をページにしたものを、何百ページも積み重ねると「図鑑」になる、というわけです。
ここまで、いろいろな仕事がありました。研究者、カメラマン、イラストレーター、デザイナー。たくさんの人が関わっていますが、最終的に図鑑は何人で作っていると思いますか?
①3人くらい
②11人くらい(サッカーチーム)
③40人くらい(学校のクラス)
正解は、3番目の「40人くらい」でした。
今、学校のクラスは何人くらいですか? 20人くらいから30人くらいでしょうかね。それよりも多い人数で図鑑は作られています。
「研究者」は、8人の先生にかかわっていただきました。東京の先生もいれば、茨城県の先生、九州の福岡の先生もいらっしゃいます。全国の先生たちに集まってもらいました。
「イラストレーター」は、15人いらっしゃいます。
「カメラマン」は、1人。
「デザイナー」は、メインは5人くらいですが、全体で10人にかかわってもらっています。
そして、真ん中にいるのが、私です。「編集者」という仕事です。
編集者の役割
編集者は何をしているのか? これだけたくさんの人たちが一斉に仕事をするので、それをまとめたり、指示を出したりします。
その前に、「どんな図鑑にすれば、読んでくれる皆さんが喜んでくれるのかな、楽しんでくれるのかな」ということを考え、誰に文章を書いてもらい、誰に絵を描いてもらうか、といったことを決めるのも、編集者の仕事です。
このようにして、皆さんが読んでくれている図鑑は作られている、というお話でした。
恐竜の絵ができるまで
もう少し踏み込んで、「恐竜の絵ができるまで」をご紹介しましょう。
先ほども言った通り、恐竜はもういませんよね。ですから、1つ1つ絵で描き起こさなければなりません。例えばこちらは、へスぺロサウルスという恐竜です。聞いたことがありますか? そう、ステゴサウルスの仲間ですね。ステゴサウルスと同じように、背中に骨の板や骨のトゲがあります。
しかし、この絵もいきなりできあがるわけではありません。皆さんも、学校の図工の時間や、幼稚園や保育園のお絵描きの時間で、いきなり絵具で描き始めることはなく、最初は鉛筆で下書きをしたりしますよね。それと同じようなことをします。
ですから、はじめはへスぺロサウルスは、こんな感じのラフなものです。この絵は、実はコンピューター上で作られています。CG(シー・ジー)と言って、コンピューターグラフィックスという技術です。鉛筆で描くのではなく、パソコンの中で粘土をこねるような形で描いていきます。まだこれ、表面はツルツルで、シワもなく、色もありませんよね。まずは形をざっくり作るところから始めます。
恐竜の絵の細かなこだわり
イラストレーターさんが作ってくださったラフを、私と、詳しい研究者の先生が見て、修正を加えていきます。
皆さんも学校のテストで、先生に「ここはこう直してね」と赤ペンを入れられることがあると思いますが、それと同じようなことをしています。
これは、私が入れた赤ペンです。例えば、背中の骨の板の枚数は、実はかなり正確にわかっているので、「もうちょっと増やしてくださいね」と修正を入れます。
他にも、「首をもっと太くしてください」といった指示や、前足の指が4本で描かれていましたが、へスぺロサウルスの前足は5本あります。ですから、「指の本数も正しく描いてください」と伝えます。
さらに細かく言うと、私たち人間の手には指の爪が全部生えていますよね。しかし、ヘスペロサウルスの爪は、実は内側の2本だけ(人間でいうと親指と人差し指だけ)にしか爪がありません。中指、薬指、小指には爪がないので、「ここには爪を描かないでね」というコメントを書いています。細かいですよね。
恐竜イラストの完成
このような細かな部分を、恐竜に詳しい研究者の先生たちと相談しながら、「こういう姿だったろうな」という形に直していくと、だんだん絵が仕上がっていきます。最初のラフな絵とは、だいぶ違いますよね。
体の表面にきちんとシワが入り、骨の形がこのように表現され、バッチリになったら、最後に「色を塗ってください」とお願いして、完成形になるのです。
恐竜図鑑を作るときは、この作業をだいたい2か月くらいかけて行います。これを何百枚も同時進行で進めていき、最終的に400枚ほどの絵が完成します。これは恐竜図鑑を作る上で一番大変な仕事ですが、同時に一番楽しい仕事でもありますね。
口を閉じて、夕日をバックにたたずむティラノサウルス
他の絵もお見せしましょう。こちらは、私が描いた、ふわっとした鉛筆画なのですが、ティラノサウルスの絵を描いてほしいと思った時に、例えば「口を閉じている姿」や、「夕日をバックにたたずむティラノサウルス」というお願いをイラストレーターさんにしました。
そうすると、このような絵ができました。すごいでしょう? イラストレーターさんは本当にすごいですよね。口を閉じて、夕日をバックにたたずむティラノサウルスです。
なぜこのような絵にしたかというと、だいたい恐竜図鑑のティラノサウルスは、口を大きく開けて「怖いぞ!」という顔ばかりしていますよね。でも、わたしたち人間も、例えば喧嘩が強い人でも、普通にシュンとしている時もあります。だから、このような少し切ない顔のティラノサウルスを見てもらうことで、「ティラノサウルスも生きてるんだな」と感じてもらえるのではないかと思って、このような絵を描いてもらいました。
トリケラトプスの群れ
もう1枚お見せします。「トリケラトプスが群れで、水場で水を飲んでいる絵を描いてくれませんか?」というお願いをした時に、私が描いた大まかな絵はこれなのですが、これを見たイラストレーターさんが、このように描いてくれました。
先ほどのティラノサウルスは1匹だけでしたが、こちらのトリケラトプスは群れで描いてもらいました。これはわざと意図的にそうしています。やはり、植物を食べる恐竜は、群れで暮らすことが多かったのです。ですから、このように植物を食べる恐竜らしさを伝えるためにも、「群れで生活している様子を絵にしてほしい」とお願いし、このような絵になりました。
図鑑制作における写真集め
カメラマンさんから写真を借りる場合
恐竜だけでなく、他の図鑑についてもご紹介します。
写真の集め方です。最初に、いろいろな図鑑があることをお話しました。例えば、昆虫図鑑にはたくさんの昆虫の写真が載っていますし、動物図鑑には犬やキリンの写真が載っています。また、地球の図鑑だと、地面に埋まっている宝石や鉱物などさまざまな写真が載っていて、図鑑にはいろいろな種類の写真が使われています。
これらの写真は、さまざまな場所から集めてこなければなりません。では、ここに載っているものを全て私たち編集者が撮りに行っているかというと、そういうわけではありません。多くの場合、素晴らしい写真を撮ってくださっているカメラマンさんからお借りすることが主な方法です。
例えば、キリンはアフリカのサバンナにいますよね。キリンの写真を撮るためだけに飛行機に乗って撮りに行くのは大変です。ですから、アフリカに写真を撮りに行っているカメラマンさんから写真をお借りしたりします。これは南極にいるコウテイペンギンですね。
このように、世の中には素晴らしい写真がたくさんありますので、そういったものを集めてくるのがほとんどです。
自分たちで撮影に行く場合
ただ、自分たちで写真を撮りに行くこともあります。
例えば、最近私たちのチームの仲間が撮りに行った写真がこれです。これは何かというと、『学研の図鑑LIVE 危険生物』図鑑に載っているワニを「本当の大きさ」で載せるための写真です。この図鑑を開くと、ワニがページいっぱいに載っていて、とても迫力があります。
なぜ自分たちで撮りに行かなければならなかったかというと、これほど大きく、アップで撮られたワニの写真が他にないからです。ではどうするのかというと、動物園にお願いして、水槽の水を抜いてもらい、ぎりぎりまで近寄って写真を撮る、ということをします。もちろん、飼育員さんが一緒にいてくれるので、安全な場所で撮影していますが、この様子だけ見ると、ちょっとびっくりしてしまいますよね。
ワニとダチョウの裏話
ちなみに、こぼれ話を聞いたのですが、このワニの写真で大きい方はオス、小さい方がメスです。本当はオスだけを撮りたかったのですが、メスが全然離れてくれなくて、「ちょっと離れて」とツンツンうながしても「いやだ!」という感じで全く離れないので、仕方なく一緒にいる状態で写真を撮ったのが、ここに載っています。
他にも、住んでいる場所は違いますが、ジャングルに棲んでいる全長10メートルにもなるようなヘビの写真も、自分たちで動物園に撮りに行きました。
これはダチョウです。ダチョウの顔のアップの写真です。この写真を撮影するとき「蹴られそうになった」とチームの仲間が言っていました。
このような写真を撮りに行くのは、やはり本を読んでくれる皆さんに、ワニやヘビがまるで目の前にいるかのような様子を届けたい、という時です。頑張って自分たちで写真を撮りに行くことがあります。
生きた昆虫の撮影
昆虫図鑑を作った時のエピソードです。これも私の仲間が作った本ですが、ちょっと変わったことをしました。
この昆虫図鑑を作るにあたり、九州大学にいらっしゃる丸山(宗利)先生と一緒に作ったのですが、丸山先生から「昆虫図鑑に載せる昆虫、全部生きたまま撮影しませんか?」という提案がありました。
よくある昆虫図鑑に載っている昆虫の写真はすべて死んでいる状態なんです。「標本」と呼ばれる、捕まえられてきちんと保存されているものなのですが、その段階で若干色が変わってしまうことがあります。
これまでの図鑑のテントウムシはこれ。今回の図鑑はこちらです。見比べてみてください。違いがわかるでしょう。こちらの方が色鮮やかで、生き生きしているように見えますよね。
丸山先生から「図鑑に載せる虫は全部生きた状態にしたい」と言われ、「やりましょう!」ということになりました。生きた状態の昆虫を撮影するためには、昆虫をすべて捕まえなければなりません。そこで、丸山先生がトップに立ってくれて、何十人ものチームを作り、全国で昆虫を捕まえまくる、ということをしました。昆虫を捕まえて、それを写真撮影して、図鑑に載せています。
捕まえた昆虫の数
ここでクイズです。昆虫図鑑のために、何種類の昆虫を捕まえたでしょうか?
①100種類
②2,000種類
③7,000種類
正解は3番目の7,000種類です。すごいですよね。
ただ、7,000種類全部載せるとなると、それこそ全3巻のような厚さになってしまい、大変です。ですから、皆さんが求めやすいように、読みやすいように、泣く泣く2,800種類まで絞って掲載しています。
図鑑は「世界の入り口」
このようなことをしながら、図鑑を作っているのですが、今日の前半戦のそろそろおしまいの話をします。「図鑑ってなんだろう?」というお話です。
皆さんも当たり前のように図書館にあったり、お父さんやお母さんも子どもの頃に読んだかもしれませんが、私たちGakkenは図鑑をこのように考えています。それは「世界の入口」です。
図鑑は1冊、分厚くて、重いですよね。たくさんの情報が載っているので、「ここに全てが詰まっている」と思われがちです。しかし、実はそんなことは全くありません。全然載っていないことも多いのです。
例えば昆虫。先ほど2,800種類を載せたと話しましたが、日本の図鑑で一番多く載っているのは、私たちの図鑑です。それでも、今地球上で見つかっている昆虫は100万種類います。2,800種類と比べると、桁(けた)が3つ違いますね。すごいですよね、これ。
しかも、まだ毎年たくさんの新しい種類の昆虫が見つかっていて、実際には500万から1,000万種類ぐらいが、今の地球にいるのではないかと言われています。昆虫はかなり新種が見つかっていて、実は、この学研の昆虫図鑑を作っている間に7,000種捕まえたら、その中に1種類、新種が見つかってしまいました! それくらい、実は新種が見つかるのですが、まだまだ見つかっていない昆虫がたくさんいるのです。
100万種を全部図鑑に載せようと思ったら、どれくらいの厚さになるのか計算してみたのですが、なんと厚さ14メートルにもなってしまいます!すごい高さですよね。
図鑑が伝えたいこと
「地球」には、ものすごく多様な生き物がいます。それに比べると、図鑑に載っていることなんてほんのちょっとなのです。図鑑に載っていないことがたくさんある、ということを、今日皆さんにはぜひ覚えて帰ってほしいと思います。
なぜなら、私が先ほど言ったように、図鑑はあくまで「入口」だからです。「こんなかっこいい昆虫がいるんだ」「こんなかわいい動物がいるんだな」「こんな美しい鳥がいるんだな」といったように、生き物に興味を持ってもらって、その後ぜひ本物を見てほしい、というのが私たちの一番の願いなのです。

休憩時間も子どもたちが囲み、質問に丁寧に答える松原氏
私たちも一生懸命頑張って、図鑑にきれいな写真を見せたり、かっこいいイラストを載せたりしています。それは何のためかというと、この素晴らしい「本物の自然」を、実際に読者の皆さんの目で見て、耳で聞いて、手で触ってほしい、という願いで作っています。
図鑑を読んだら、ぜひ公園に行ってみたり、動物園、植物園、水族館に行ってみたりして、図鑑をきっかけに自然と触れ合っていただけたらと思います。
いったんここで図鑑の作り方のお話は終了です。休憩をはさんで、後半は生き物のクイズを皆さんに解いてもらいながら、最終的に地球のことについて考えるお話をしたいと思っています。
「世界の生き物クイズ大会」と「知ることの大切さ」
後半を始めていきたいと思います。
「世界の生き物クイズ大会」ということで、皆さんに解いてもらいたいクイズを10問用意しました。先ほどのように3択で手を挙げてもらいながら、その生き物の解説をしていきたいと思います。その上で、地球環境の話もしていきたいと思っています。
生き物クイズに挑戦!
まずは昆虫に関するクイズをいくつか出題します。
第1問:コウチュウの仲間は、何種類見つかっている?
①15万種くらい
②26万種くらい
③37万種くらい
ここにいるのは日本のカブトムシですね。カブトムシはコウチュウ(甲虫)の仲間です。コウチュウは体が硬い昆虫を指します。
先ほど昆虫は100万種類見つかっていると話しましたが、その中でコウチュウはどれくらい見つかっていると思いますか? 少し難しいかもしれませんが、皆さんならきっとわかりますよね。
正解は3番目の「37万種くらい」でした!
コウチュウって、本当にたくさん見つかっているんですよ。100万種の中でも37万種類というのは多いですよね。
昆虫には他にもチョウの仲間やカマキリなど、色々な種類がいますが、コウチュウといってもカブトムシだけでなく、クワガタやテントウムシ、ホタル、タマムシなど、体が硬そうな昆虫は大体コウチュウの仲間に入ります。約37万種類もいるグループだと分かると、生き物の見え方も変わってきますよね。
第2問:アリとアブラムシの関係で正しいのは?
①アリがアブラムシをまもる
②アリがアブラムシを食べる
③アリがアブラムシに乗る
アリとアブラムシは、ある特別な関係を持っています。それは何でしょう?

生き物についてのクイズ
正解は1番の「アリがアブラムシをまもる」でした。
アリがアブラムシを守っている。これ、どういうことか説明しますね。アブラムシは小さくて弱い昆虫です。アブラムシを食べる虫がいます。皆さんよくご存知のテントウムシです。アブラムシはテントウムシに食べられてしまうのですが、それを守ってくれるのがアリなんです。アリは非常に強い力を持っていて、アブラムシを守ってくれます。では、アリはただでアブラムシを守ってくれるのでしょうか?
アブラムシはお尻から汁を出していて、アリはそれを食べます。そのお礼としてアリはアブラムシを助けるんです。アブラムシもアリに対して、この食べ物を渡し、その代わりにアリに守ってもらう、という関係性なんですね。
このような助け合いの関係を、共に生きると書いて「共生」(きょうせい)と言います。実は地球上に住んでいる生き物は、このような共生関係をたくさん築いているんです。
他にはどんな例があるかな。例えば、大きな魚の口の中の歯を掃除する魚、ベラの仲間の魚がいたりするのを知っていますか?
はい、ホンソメワケベラですね。大きな魚は、歯を掃除してもらう代わりに、そのベラの仲間を守る、という関係性があります。実は地球上の生き物は、助け合って暮らしているんですね。
第3問:セミの幼虫の食べ物は何?
①かれた葉っぱ
②木のしる
③小さな虫
アブラゼミとアブラゼミの幼虫をスクリーンに写していますが、夏になるとセミの抜け殻が公園などにたくさんありますよね。さて、このセミの幼虫は何を食べているでしょう?
正解は2番、「木のしる」でした!
このセミの幼虫がどこにいるのかというと、実は土の中にいます。公園などで、この幼虫がウロウロしているのを見たことはないですよね? セミは卵を木の中に産み、幼虫は土の中で成長します。そして、いよいよ成虫になるタイミングで、夜中にモゾモゾと地上に出てきて、そこでバカっと殻を脱いで成虫になり、セミの姿に変化するんです。
土の中で何をしているか?というと、セミの幼虫は木の根っこなどから汁を吸って暮らしています。目に見えないところにもたくさんの生き物がいる、というひとつの例ですよね。公園に6月や7月に行って、たくさんのセミの抜け殻を見つけたら、「地面の下にはたくさんのセミがいるんだな」と思うと、楽しいと感じる人と、ゾクゾクする人がいるかもしれませんね。そんな想像をしてみるのもいいかもしれません。
第4問:スズムシの「耳」はどこにある?
①頭
②前あし
③おなか
スズムシを飼ったことがある人いますか? かなりいますね。私も小学校の時にスズムシを飼っていました。秋になると「リリリ…」と鳴いて、家がずっと賑やかになりますよね。
そのスズムシの耳についてのクイズです。スズムシの耳はどこにあるでしょうか?
答えは2番の「前あし」でした。
よく見てください。前あしに米粒のような白い部分があるのがわかります。これが音を聞く部分なんです。無理やり人間になぞらえると、この肘あたりで音を聞いていることになるんです。なんかすごいですよね。
昆虫と私たちを含む哺乳類などは、やはり体の作りが全く違います。例えば、私たちの体を支えている骨は体の中にありますよね。中に骨があって、周りに柔らかい筋肉や皮膚があります。けれども、昆虫は「外骨格」といって、体の外側が硬くなっていて、内側が筋肉になっています。まるで私たちの体の作りと逆のようなことになっているんです。
頭があったり足があったりする点は変わりませんが、昆虫の足は6本あったりしますしね。音を聞く部分も、私たちは脳の近くに耳がありますが、スズムシは前足に音を聞く部分があるんです。びっくりしますよね。スズムシの見方がちょっと変わってきますよね。
ここまでが昆虫クイズでした。
動物クイズに挑戦!
第5問:チーターが獲物(えもの)を追いかける速さは?
① 新幹線くらい(時速約260キロ)
② 電車くらい(時速約110キロ)
③ 車くらい(時速約60キロ)
チーターはめちゃくちゃ速く走る動物です。チーターが獲物を追いかける速さはどれぐらいでしょうか?
2番に手をあげた人が多かったですね。答えは2番、「電車くらい」が正解でした。時速110キロです。みんなバシバシ当ててきますね、素晴らしい!
先ほど昆虫は私たちと体の作りが違うと話しましたが、チーターは私たちと同じ哺乳類です。ですから、体の作りは似ているところも多いんです。では、「時速110キロで走ってください」と言われたら、私たちは無理ですよね? でも、チーターはそれができてしまうんです。その秘密の話をしましょう。
この写真では、背中をグッと曲げている状態ですが、この後、足をバッと広げて、体も伸ばします。そうすると、背中もグニャンと引き伸ばされます。この時の背骨が、縮んだり伸びたりするバネのような動きで、ものすごい力を前に前にと作り出すんです。チーターは全身を使って前に進んでいくことで、時速100キロ以上のスピードを出すことができる、そんなすごいパワーの能力を持っています。
チーターの豆知識をもう少しお話させてください。ガゼルやインパラなどを追いかける際、チーターが時速110キロで走ると、急に曲がるのは大変ですよね。チーターはカーブする時に、ある体の部位を使って曲がっているのですが、知っている人はいますか?
そうです。曲がる時に尻尾をブンと振ってカーブをするんです。例えば、イメージすると、くるくる回る椅子に座っている時に、腕をクンと振ると体が回る、というのと同じですね。勢いよく腕を振ると、それで重心が動いて回る、ということがあります。チーターがカーブをする時は、尻尾を振ってカーブします。
あともう一つ、チーターを語る上で言っておかなければならないことがあります。それは「爪が出っぱなし」だということです。
猫は、普段は爪がしまわれていて、時々ピュッと出しますよね。猫の仲間は爪を出し入れすることができるのですが、チーターは猫の仲間であるにもかかわらず、爪が出っぱなしなんです。この爪は、走る時の地面を掴む、スパイクの役割をします。サッカーの選手などが履く靴って、トゲトゲのスパイクがついていますよね。速く走る人たちは靴のトゲトゲで地面を捉えるのですが、それと同じような役割として、チーターは爪を使っているという話でした。
第6問:ヤマアラシの攻撃(こうげき)方法は?
①とげをとばす
②とげをたてて、まるくなる
③とげをたてて、うしろむきにはしる
ヤマアラシは何の仲間かというと、ネズミの仲間なんですね。かなり大きいんですよ。ハリネズミと混同している人がいるかもしれませんが、ハリネズミは手のひらに乗るくらいですが、ヤマアラシは大きいです。
そのヤマアラシの攻撃方法は、ちょっと穏やかではありません。このトゲトゲで身を守るのですが、では、どうやってこのトゲトゲを使って敵に襲われた時に攻撃するのでしょうか?
答えは3番目の「トゲをたてて、後ろ向きに走る」でした。
よく図鑑にも、トラがヤマアラシを襲っているような写真を載せているのですが、ヤマアラシは敵にお尻を向けて、このトゲを逆立てて見せ、バックして突撃するんです。そうすることで、このトゲを刺すのですが、このトゲは細かく「返し」がついています。だから刺さると抜けにくいんですよ。しかもこのトゲはヤマアラシからは抜けやすくなっているので、グサッと刺さると自分からはスポッと抜けて、相手にトゲが残るという、なかなか強力な武器だったりもします。ネズミの仲間と言いつつも、ヤマアラシは強いやつだと私は思っています。
第7問:この中で毒を持っているのはどれ?
①ビーバー
②カワウソ
③カモノハシ
答えは3番目の「カモノハシ」でした!
カモノハシってすごいんですよね。まず毒の話からしましょうか。オスのカモノハシの写真を持ってきました。後ろ足に何か大きなトゲのようなものがありますよね。このトゲに毒を持っています。どれくらい強い毒かというと、小さい犬などが刺されると、だいぶ危険なことになってしまうくらい、なかなか強い毒だと言われています。
他にもカモノハシは、すごく面白い特徴を持っています。私たちと同じ哺乳類という仲間ではあるのですが、その中でも少し原始的な生き物で、なんと「卵を産む」というのも知られています。哺乳類は、人もそうですし、犬や猫、ライオンなど、赤ちゃんをお母さんのお腹の中で育てることが多いですよね。しかし、カモノハシは哺乳類でありながら、鳥や爬(は)虫類のように卵を産むという点で、とても面白い生き物だと言われています。
第8問:このカエルの武器(ぶき)は何?
①毒がある
②強い力で、かみつく
③するどい爪がある
正解は1番の「どく(毒)」です!
これは「ヤドクガエル」という、ジャングルに生きている、本当に小さなカエルです。けれど、これは皮膚に毒があります。現地で暮らしている人たちは、この毒を吹き矢に塗って、狩りをする時に使ったので、「矢の毒のカエル」で「ヤドクガエル」という名前がついています。めちゃくちゃ強い力を持っています。
これは「イチゴヤドクガエル」という、イチゴのような赤い種類ですが、他にも黄色いヤドクガエルなど、いろいろいますね。
ちなみに、このような毒を持っている生き物は、大抵、派手な色をしていることが多いです。これは「自分は危険だぞ!」というアピールなんです。目立ちますよね? ジャングルの中にいたら、多分すぐわかります。あえて自分を危険な色に見せることで、「危ないから食べても美味しくないぞ!?」という風にアピールをしていると言われています。
第9問:ハリセンボンのとげは何本ある?
①約100本
②約300本
③約1,000本
答えは約300本でした!
正確には340本くらいらしいのですが、たぶん個体差があるのでしょう。
敵が来ると、ハリセンボンはフグの仲間なので、体を膨らませますよね。水を吸って体を膨らませ、体を大きく見せるのですが、さらにハリセンボンは体にトゲを持っています。そのトゲがあるおかげで敵に食べられにくくなっています。それでは、このトゲは何だと思いますか?
実は「鱗(うろこ)が進化したもの」なんです。魚を食べる時、魚の体の周りに鱗がついていますよね。もしかすると、お家で魚をさばく時に鱗を取ることもあるかもしれませんが、普通の鱗って平たいピラピラしたものですけど、それがトゲに変化しているのがハリセンボンなんです。
第10問:恐竜から進化したと考えられている生き物は?
①とり
②ワニ
③ライオン
正解は、1番の「とり」です!
恐竜は約6600万年前に、隕石が地球にドンと衝突して、それでいろいろな恐竜が絶滅してしまったと言われています。恐竜は、三畳紀(さんじょうき)、ジュラ紀、白亜紀という3つの時代で生きていましたが、その真ん中のジュラ紀という時代には、すでに恐竜の中から、羽毛を持って飛べる仲間が生まれていました。それが鳥の祖先です。そこからどんどん進化もしていて、実は白亜紀のティラノサウルスなどが絶滅したタイミングで、もう鳥はいたんです。そして、生き残って今に至ります。
「鳥は恐竜とも言える」と、言われています。「恐竜が鳥に進化した」とも言えますし、あとは「恐竜は生きている」とも言うわけですね。ここに持ってきたのはスズメですが、足だけ見ると、ちょっと恐竜っぽいですよね。そういうこともあり、「今も恐竜が生きている」というお話です。
知ることから始まる、新しい世界の見え方
ここまでクイズを出してきましたが、「なぜこんなクイズを突然出したの?」という、理由を最後にお話ししたいと思います。
ここで私が今日皆さんに一番伝えたいなと思うのは、「知ること=世界の見え方がかわること」です。例えば、「スズムシはどこで音を聞いているの?」「前あしで聞いてる!」という話を聞いて、皆さん驚きましたよね。私も初めて知った時は本当にびっくりしました。この事実を知ると、スズムシに対する見方が変わってきませんか?
知ると、見え方が変わってくる。これは当たり前のことかもしれませんが、何事においても大切なことです。今日は地球環境についての講演に呼んでいただきましたが、地球のことを考える上でも、この「知ること」が一番のスタートではないかなと私は考えています。
地球を知ることからはじめよう!
だからこそ、「地球を知るところからはじめよう!」ということをここに書きました。
今日、皆さんにクイズを解いてもらったことにも繋がってきます。「カブトムシをはじめとしたコウチュウは30万種類以上いるんだ!」ということがわかると、世界のイメージが少し変わってきませんか? 「カモノハシには毒があって、カワウソには毒がないんだ」ということもわかりますよね。
他にも、恐竜図鑑を読めば、昔は12メートルの大きな恐竜がいたことがわかります。チーターが速く走る仕組みを知ると、私たちと同じように背骨を持つ生き物なのに、生きている環境や食べるものが違うだけで、こんなにも進化するんだな、と発見があります。ハリセンボンの針が300本であることや、ジャングルには毒を持ったカエルもいるんだ、ということなどもわかってくるでしょう。
皆さんが普段暮らしているのは小学校の学区内、おそらく半径1キロか2キロほどの生活範囲だと思います。しかし、図鑑を読むと、地球の裏側のことまで知ることができますし、何億年前のことまで思いを馳せることができます。そうすると、感じられる世界や時間がどんどん広がっていき、今自分が生きている場所がどんなところなのかが、より理解できるようになります。
「親しむ」から「大事にする」へ
それもやはり「知るところ」から始まります。皆さんも、例えば新しい学年になり、クラス替えをして、新しい友達ができると、だんだん「この子にはこういう良いところがあるんだ」「こういう面白いところがあるんだ」「算数が得意なんだな」といった発見がありますよね。そうすると、どんどん親近感が湧いてきて、「友達を大事にしよう」と思うはずです。
これと同じだと思います。「毒があってすごいな」「かなりたくさんいるんだな」とか、「ハリセンボンは針300本しかないんだな」とか、そういうことがわかってくると、また親しみが湧いてきます。親しむというところから、「大切にする」ということに繋がっていくと思うのです。
今日のこの話を地球に結びつけて考えると、地球はめちゃくちゃデカいじゃないですか。それをいきなり「守らなきゃだめ!」と言われても、「僕はスーパーヒーローじゃないんだから、そんなのできない」と感じてしまうかもしれません。
しかし、図鑑を通じて親しみ、「知る」ことから何事も始まってくるのではないでしょうか。これが、今日私が皆さんへ一番お伝えしたかったことです。
図書館や学校、本屋さんなどで図鑑を見かけたら、「あの時、図鑑を作ってる人がそんなことを言ってたな」と、今日の話を思い出してもらえたら嬉しいです。そして、皆さんが大人になってきた時に、例えばゴミを分別するといった場面で、さまざまな地球の生き物たちに思いを馳せてもらえたら、嬉しいなと思っております。
これで私のお話は終わります。ありがとうございました!
質疑応答
昆虫の変態、なぜするの?
質問:昆虫は卵から、幼虫、さなぎ、成虫と姿がだんだん変わっていくけど、僕たちの姿があまり変わらないのはどうして?
松原:あえて難しめに言うと、「なぜ昆虫は変態をするのに、僕たちは変態をしないのですか?」ということですね。
昆虫は大きく分けて、幼虫、さなぎ、成虫と体の形をガラッと変える「変態」をします。幼虫の時期は葉っぱをたくさん食べて体を大きくすることに集中します。成虫になると、実はあまり食べません。全く食べない種類もいます。オスとメスが交尾をして卵を産み、子孫を残すことに特化します。このように、それぞれの成長段階で「やること」を明確に分けているんです。
一方、私たち人間は、赤ちゃんから子ども、大人へと、ゆっくりと成長していきます。さなぎになり、背中がパクっと割れて、新しい私たちが出てくることはないですよね。大きな変化はないけれども、脳が大きく成長する時期があったり、子孫を残すために体が成熟する時期があったりと、成長の段階によって体の変化があります。体の変化があるという点では、昆虫と似ている部分もありますね。質問に明確に答えられていないけれども、生き物の生き方の方法が、少し違うということです。
恐竜のDNAは採取できる?
質問:恐竜の化石からDNAを取ることはできますか?
松原:恐竜の化石からDNAを取り、恐竜を復活させるという映画『ジュラシック・ワールド』や『ジュラシック・パーク』がありますよね。実はいまも研究者が恐竜の化石にDNAが残っていないかと注目しています。なぜかというと、DNAは生き物の体の設計図だからです。恐竜の体の設計図がわかることで、現在の鳥類や爬虫類、私たち人間との違いもわかるようになるからです。
しかし、残念ながら現状ではDNAを見つけるのは難しいと言われています。DNAは長い時間が経つと壊れてしまい、ぐちゃぐちゃになってしまうからです。6600万年前、あるいは何億年も前の恐竜のDNAが完全に残っている可能性は低いと考えられています。
ただ、科学技術は日々進歩しています。2010年頃から、化石から恐竜の色素の痕跡が見つかるなど、以前は不可能と思われていたことが可能になる例もあります。もしかしたら、何十年か後には、今は無理だと言われているDNAの採取も、新たな研究方法によって可能になるかもしれませんね。そこは楽しみに待っていたいですね。
チーターの背骨を解明するには
質問:チーターの背骨は、どうやって調べたのですか?
松原:調べる方法はいくつか考えられます。まずは外から観察することです。研究者は、チーターが走る様子を撮影し、背骨がどのように曲がり伸びるかを詳細に分析することで、その動きと走り方との関係を推測したようです。
チーターの骨格標本からの研究も考えられます。もし死んだチーターの骨格が見つかれば、それを持ち帰って詳しく研究、観察することができます。
コンピューターシミュレーションも活用されています。チーターのような体型の動物が時速110キロで走る場合、どのように体を動かせば効率的なのかをコンピューター上で計算することができます。
実際に生きているチーターに「もっと走って!」と頼むわけにはいかないので、研究者たちはさまざまな観察や分析、シミュレーションといった方法を組み合わせて、チーターの背骨の秘密を解き明かしてきたと考えられます。
恐竜の大きさは?
質問:恐竜はどのくらいの高さですか?
松原:恐竜の大きさ、高さの話ですね。「高さ」と「長さ」は少し違います。「長さ」でいうと、例えばスーパーサウルスのような竜脚類は、頭の先から尻尾の先までの全長が20メートルから30メートルにもなります。
「高さ」でいうと、首をどれくらい上まで持ち上げられたかという話になります。例えば、ブラキオサウルスのような恐竜は、15メートルくらいまで首を上げられたと言われています。これは、およそ5階建てのビルに匹敵する高さです。
このように、長さが20〜30メートル、高さが15メートルほどもある大きな恐竜がいました。
昆虫に背骨はある?
質問:背骨がある昆虫はいますか?
松原:昆虫には、私たち人間や魚、爬虫類、両生類、鳥類のような背骨はありません。
背骨がある動物は「脊椎動物(せきついどうぶつ)」と呼ばれますが、昆虫は脊椎動物とは異なる進化の過程をたどってきました。昆虫の体は、体の内側に骨があるのではなく、体の外側が硬い殻で覆われていて、それが鎧(よろい)のように体を支えています。
もし体の中に背骨がある昆虫が見つかったとしたら、それは昆虫とは全く違う、新しい種類の生き物として大発見になるでしょう。現在生きている昆虫には、体の中に背骨や骨はありません。
チョウのさなぎの中身ってどうなってるの?
質問:チョウのさなぎの中では何が起こっているんですか?
松原:チョウのさなぎの中では、幼虫の体が成虫の体に作り変えられるという、とても大きな変化が起こっています。
よく「ドロドロに溶けている」と言われますが、本当に液体になってしまうわけではありません。体の中で、成虫に必要な新しい部分が作られ始めるんです。
例えば、幼虫にはなかった羽が作られたり、幼虫の足とは形が違う、成虫の長い足が形成されたりします。カブトムシのさなぎの中では、特徴的な角(つの)が作られていきます。カブトムシの角は、実は最初から長い形をしているのではなく、風船のようにクシャクシャになった状態から、だんだんふくらんで伸びていくという研究もあるんですよ。実は日本人の先生が研究しています。
このように、さなぎの中では、全く異なる姿の成虫へと変化するための準備が進められています。
生き物が進化する理由とは?
質問:どうして進化するんですか?
松原:ダーウインが「進化論」を提唱しました。進化の「なぜ?」は難しいのですが、簡単に言うと、生き残りやすさと子孫の残しやすさが関係しています。
生物は皆、生き残って子孫を増やそうとします。例えば、キリンの首が長いのは、高い木の葉を食べられる個体が生き残り、より多くの子孫を残すためです。その結果、首の長いキリンが増えていったと考えられています。
このように、環境に適応し、生き残るのに有利な形質を持った個体が子孫を多く残し、その形質が代々受け継がれていくことで、結果的に生物の形が変化しているように見えます。私たちはこの現象を「進化」と呼んでいます。
スーパーサウルスの赤ちゃんの大きさは?
質問:スーパーサウルスの赤ちゃんはどれくらいの大きさですか?
松原:スーパーサウルスの卵が見つかっているかどうかはわかりませんが、最近、博物館で、スーパーサウルスよりも少し小さいくらいの竜脚類の恐竜の卵の化石を見てきました。それらから推測すると、スーパーサウルスの赤ちゃんが孵化(ふか)したばかりの時は、抱えられるくらいの大きさだったと考えられます。そんなに大きくはないですね。
大型の恐竜の卵は、体の大きさに比べて意外と小さかったようです。彼らは子育てはあまり得意ではなかったようですが、小さな卵をたくさん産み、その中から生き残った個体が成長していくという方法をとっていたと考えられます。
恐竜って全部で何種類くらいいたの?
質問:恐竜は今までにどのくらいの種類がいたのですか?
松原:今のところ、恐竜は約1,000種類が見つかっていると言われています。しかし、地球上にはもっと多くの種類の恐竜が生息していたと考えられています。何万種類もの恐竜がいた可能性も十分にあります。例えば、現在、魚だけでも約3万種類いると言われていますから、恐竜も数千種類から1万種類以上はいたのではないでしょうか。正確に答えられていませんが、今見つかっているよりもたくさんいたと思います。
人間に尻尾(しっぽ)がないのはなぜ?
質問:なぜ人間には尻尾がないの?
松原:私たち人間は、サルから進化してきたので、もともと私たちの祖先には尻尾があったと考えられます。チンパンジーやゴリラ、オランウータンなど、私たちに近い仲間も尻尾を持っていませんね。尻尾が退化して短くなった、と考えられています。
かつて木の上で暮らしていた頃は、尻尾を使って枝をつかんだり、バランスを取ったりと便利だったかもしれません。しかし、私たちが地面に降りて、二足歩行をするようになると、尻尾はむしろ邪魔になってしまいます。生物の進化の傾向として、必要のないものはだんだん短くなったり、なくなったりすることがあります。
そのため、私たちが直立して生活する上で尻尾が不要になった結果、現在の私たちには尻尾がない、と考えるのが自然でしょう。
地上で一番強い動物は?
質問:アフリカゾウが動物で最強ですか?
松原:アフリカゾウが地上最強かどうか、確かに気になりますよね。私も、アフリカゾウは相当強いと思います。
何と言っても体が大きく、体重があるため、その打撃力やパワーは圧倒的です。現在、地上に暮らす陸上の哺乳類の中では、アフリカゾウが最も大きく、重い動物です。その意味で、アフリカゾウが最強であるという考えはとても理にかなっています。
ホッキョクグマとアフリカゾウが本気で戦ったら、アフリカゾウが有利なのではないでしょうか。キバも長いですしね。
昆虫にも病気はあるの?
質問:昆虫にも病気はありますか?
松原:あると思います。私たち人間と同じように、昆虫も生き物だからウイルスに感染したり、さまざまな病気にかかったりすることはあると思います。
具体的な昆虫の病気については、すぐにはお答えできないので、もっと勉強しておきますね!
昆虫も呼吸するの?
質問:昆虫も呼吸しますか?
松原:昆虫も呼吸をします。地球上に生きている生物は、基本的に皆、呼吸をしないと生きていけません。ただし、私たち人間と昆虫では、呼吸の仕方が少し違います。私たちは鼻や口から息を吸って、肺で呼吸をしますが、昆虫は主にお腹のあたりで呼吸をしています。
昆虫のお腹には「気門(きもん)」と呼ばれる小さな穴がいくつか開いていて、そこから空気を取り込んでいます。鼻や口から息を吸うのではなく、お腹の気門を使って呼吸しているんですね。図鑑などで昆虫のイラストを見ると、お腹のあたりにボツボツ小さな穴が並んでいることがありますが、それが空気の通り道、気門です。
動物のDNAを混ぜて新しい動物は作れる?
質問:動物のDNAと別の動物のDNAを混ぜて、新しい動物を作ることはできますか?
松原:混ぜることだけではできないと思います。DNAは生物の「設計図」のようなものですから、単純に動物のDNAを混ぜるだけでは、新しい動物を作ることはできません。
しかし、DNAの設計図を書き換えることで、体の形を少し変えたり、新しい特徴を持たせたりすることは、原理上、可能です。
例えば、植物の品種改良では、すでにそのような技術が使われています。ジャガイモとトマトを掛け合わせて作られた「ポマト」は、DNAの組み合わせや書き換えによるものです。
ただし、生き物の遺伝子やDNAを操作する際には、倫理的な問題や、それが生物にどのような影響を与えるかを慎重に考える必要があります。適切なルールを作り、節度を持ってDNAと向き合っていくことが大切です。
動物の種類が違うのはなぜ?
質問:なぜ動物って種類が違うんですか?
松原:動物にさまざまな種類がいる理由のひとつは、地球上に多様な環境があるからです。
地球上には、寒い場所、暑い場所、高い山、深い海など、いろいろな環境がありますよね。生き物は、それぞれの環境で生きていかなければなりません。その場所で一番暮らしやすいように、体の形や生き方が変わっていきます。例えば、深い海で暮らす魚と、浅い場所で暮らす魚では、全く違う形をしていますよね。
最初の生命は1種類だったかもしれませんが、地球のさまざまな場所で暮らすために、いろいろな種類が増えていったと考えられます。
昆虫に心臓はあるの?
質問:昆虫に心臓はありますか?
松原:昆虫には、私たちのように、胸に手を当てるとドクドクするような「心臓」があるわけではありません。しかし、昆虫の体の中にも、血を体中に巡らせるための、心臓に近い役割を持つ場所が存在します。
他に質問がある方は、会場の時間が許す限り、個別に対応させていただきます。
本日はありがとうございました!
当日レポートはこちらをクリック
講演会の様子、展示の内容などをねり☆エコのレポーターがご紹介いたします。